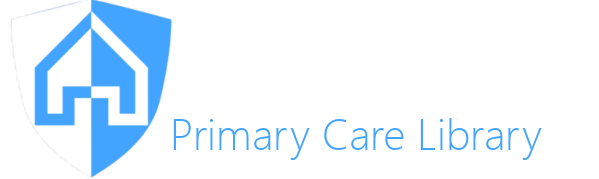ライフレビューと脳科学の関係
wandering_cat
- Reviewed:
- Olaf_lover
- Arnab
- Ryo

Neuroscience: Idle minds
★論文の内容:
1990年代半ばからの脳科学研究では、特定のタスクを行っていない間にも規則的な脳活動があることが発見され、この「休止状態(resting state)」における脳活動に関する研究が行われるようになった。
休止状態にみられる脳活動に関する研究はほとんどの場合仮説レベルにとどまるが、記憶の整理や固定化のほか、過去の記憶や経験をパターン化し、次に起こる現象に対して準備する役割があるのではないかと考える論文や研究者がいる。
★ディスカッション:
九州大学心療内科主催のセミナーで細井昌子先生の講義中に紹介されていたNatureのarticle。慢性疼痛に関する診察でライフレビューを行うことにより、患者一人ひとりが持つ独特な認知・情動・行動パターンの解明に繋がり、そのことが疾患理解と治療に役に立つ、という文脈での紹介であった。つまり、過去の記憶や経験を紐解いていくことで、その患者が出会う様々な現象に対してどう反応するのかを知ることができ、いわばその「反応スタイル」は「休止状態」の脳活動が担っているのかもしれない、という考えだ。
家庭医・総合診療医の外来や、総合診療科の学生・研修医の研修では、ライフレビューを行うことがある。多くの場合これは「時間があるときに限って」「その人の価値観や考え方を知るために」行われているものであり、診療の中心ではなく周辺に置かれていることだろう。
しかし、心身相関の切り口から、各種の心身症やMUS(Medically Unexplained Symptoms)はもちろんのこと、生活習慣やその人の置かれたコンテクストが疾患の経過や治療効果に関わってくる疾患に関してはすべて、患者一人ひとりが持つ独特な認知・情動・行動パターンを踏まえた介入が重要なのではないか(特にbiomedicalな介入が決定的な結果をもたらすことが相対的に少ないプライマリ・ケアではなおさら)。
ライフレビュー等による患者の全人的理解は、単なる牧歌的な医療観に基づくお気持ち医療や、医療者のお人好し感情に根ざした象徴的な儀式でもない。
患者中心性の核となるコンテクストや病の体験、解釈・期待・感情・影響(いわゆるFIFE)をきちんと理解する、というステップを踏むこと、そこを起点として共通の理解基盤を見つけるというフレームワークを医療者が持っているかどうかで、具体的な治療効果や患者を取り巻く「システム」が変わってくるということが「患者中心の医療の方法」のポイントだろう。それはすでに現代医学におけるEBMの一要素でもあり、「EBMと併存するなにか」でもなければ、「EBMと対置されるなにか」でもない。
患者の症状や治療効果に影響する、患者一人ひとりが持つ独特な認知・情動・行動パターンに関する脳科学的な研究も、こうした考えを更に後押ししてくれると良いが・・・。
参考文献、引用
- Smith, K. Neuroscience: Idle minds. Nature 489, 356–358 (2012).
- 細井昌子. 2023九大新春心療内科セミナー講演_慢性疼痛に対する心身医学的アプローチ.
仲間と一緒に
自学する。
Primary Care Libraryでは、執筆チームに参加してくださるプライマリ・ケア医、プライマリ・ケアに関心のある領域別専門医、またプライマリ・ケアの研究や実践の関心のある医療専門職の方を募集しています。移動の合間で読んだ論文を、記事にして読者とディスカッション。臨床現場と理論を各自のペースで繋げていきます。
日本最大級のプライマリ・ケアに関するオンラインJournal Clubの運営に、あなたも参加してみませんか?